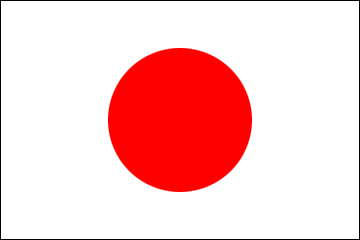歴代大使略歴
原 聰 大使(2005年10月~2008年9月)

|
1947年 8月 |
熊本県に生る(本籍佐賀県) |
|
|
1966年 |
熊本高校卒業 |
|
|
1973年 |
英国オックスフォード大学 |
|
|
1969年 |
外務公務員上級試験に合格して1970年外務省に入省。 |
|
|
1996年 |
OECD(経済協力開発機構)東京センター所長 |
|
|
1999年 |
在トロント総領事 |
|
|
2001年 |
ブルネイ駐箚 特命全権大使 |
|
|
2003年 8月 |
衆議院 外務調査室長・常任委員会専門員 |
|
|
2005年10月 |
ポルトガル駐箚 特命全権大使 |
この度、約2年10ヶ月間のポルトガル勤務を終えて、9月末にポルトガルを離れ帰国の途につくこととなりました。私は、ポルトガルという魅力的な国で大変充実した時を過ごせたことを非常に嬉しくかつ誇りに思っています。
<ポルトガル人と日本人の間の相互の憧れ>
ポルトガルは、ほとんどの日本人が強く親しみを感じる国です。それは、もちろん、16世紀に遡る両国国民の交流の歴史があるからです。でも、それだけではありません。15世紀からポルトガル人たちは、当時の小さなカラベラ船に乗って大西洋に船出し、アフリカを経てインド洋や、更には太平洋へと船を進めた、いわゆる大航海時代を築きました。そのポルトガル人の恐れを知らぬ「冒険心」に心打たれるものがあるからに違いありません。
そのような日本人のポルトガルに対する親近感と同様、ポルトガルの人々も日本に対して暖かい気持ちを持ってくれているようです。それは、歴史的交流もあるでしょうが、むしろ 、日本の伝統文化の素晴しさに加えて、明治維新以来の日本の発展というものが日本の伝統文化を犠牲にすることなく成し遂げられてきていることに対する、一種の憧憬の念があるように思われます。日本を訪問した多くのポルトガルの友人たちは、私に、東京は大変に発展した、また西洋化した大都会だが、そこで暮らす日本人たちは今なお魅力的な伝統文化も保持してきている。近代的な生活と伝統的な文化が同居する、まことに世界でも珍しい国だ、という感想を述べていました。日本の良さは、伝統文化を失わない日本人の生き方にあるようです。
そのような両国民の間の橋渡しとなるという役割を受け持った、この3年弱のポルトガル在勤は、私に多くの思い出を残してくれました。それを少しご披露しましょう。
<ポルトガルの魅力>
まず、私は、ポルトガルに着任後、恋に陥ってしまいました。この“美人”の相手は、ポルトガルの素晴らしい「赤ワイン」です。私は、昔から赤であればボルドーやイタリアのワインを、また、白であればブルゴーニュのワインを好んで来ました。それが、ポルトガルに来たら、別の“美人”に現を抜かしたというわけです。私の家内はちょっと嫉妬したのではないでしょうか。
また、ワイン以外にも、ポルトガルの抜けるような青空、モンサラーシュやマルヴァオンなどの丘の上に静かに佇む小さな村々、ジェロニモシュやバターリアなどの素晴らしい世界遺産、どの街にも見られる石畳の道と昔ながらの家々、素晴らしいゴルフ場、美味な海の幸、そして何にもまして大切なのは、ポルトガル人の心の温かさ、などなど、心に残る快適な思い出は尽きることがありません。
更に、ポルトガルにはポルトガル人が世界に誇れる素晴らしいシステムがあります。まずは、「Multibanco」です。こんな便利なシステムはほかの国ではまだお目にかかりません。次に、「Via Verde」。単に高速道路のみならず、各地に駐車場でも使える便利な支払いシステムです。第三に、ポルトガルの道路や橋の一部は、PPP(Public Private Partnership)と呼ばれる方式によって建設されています。単に国民の税金だけでなく、民間の資金力や技術を活用したこの制度は、Vasco da Gama橋などの建設に用いられてきています。私は、このような優れたシステムは日本でも活用できるものだと思います。
さて、政治や経済などの少し難しいお話もしてみましょう。
<両国は先進民主主義国として多くの価値観を共有>
現在、世界は、テロ・ナショナリズムの台頭、気候変動問題、原油・食料価格の高騰、金融市場の緊張など、非常に多くの課題に直面しています。この様な中、日本とポルトガルは、自由、民主主義、基本的人権、法の支配、市場経済など共通の価値観を有する事実上の同盟国(a de facto ally)です。これは実に大切なことだと思います。ポルトガルをはじめとするEU諸国と日本とは同じ価値観を有しているのです。同じ価値観を共有する日本とEUは、世界の平和と安定を維持し、世界経済の舵取りのために一緒に働くことが求められています。ポルトガルと日本は、このような世界的規模の問題の解決に向けて共に協力していくことのできる重要なパートナーなのです。
今日、世界には192の国があります。その中で、日ポ両国が共有している価値観と同じ価値観を有している国は、いったい何ヵ国あるでしょうか。決して多くはないのが現実だと思います。ポルトガルと日本は、先進民主主義国として、上に述べたような多くの価値観を共有しているのです。このことは、両国関係を考えるとき、忘れてはならない基本だと思います。
私は、2005年11月にポルトガルに着任して以来、長い友好の歴史を有する両国間の関係を更に発展・深化させるべく努力して参りました。主なところでは、
»葡日友好議員連盟再結成に向けた働きかけ(2006年7月に再結成)
»2007年2月アマード外相訪日及び08年3月のガマ国会議長訪日の実現
»日本企業と協力してのリスボン観光フェアへの参加
»日ポ姉妹都市交流の活性化と新規姉妹都市提携に向けた働きかけ
»「JapanNET」の設立(ポルトガルで活動している日本関係諸団体間のネットワーキングのための定期的会合)
»アジアの安全保障情勢・日本経済の動向・日本人の価値観などと題した各種講演会
»ポルトガル人で日本の友人たちを招いた「Friends of Japan」ガーデン・パーティの開催
»天皇誕生日レセプションへの日系企業協賛参加
»日本関係企業交流促進会の開催
»大使表彰の実施
»在留邦人のための新年会開催
»日本語補習校生徒のための餅つき大会
»和太鼓公演・アニメ講演会などの日本文化紹介事業等を実施してきました。公邸にはポルトガルの要人の方々をお招きして、日本の最も格式高い「懐石料理」でおもてなしし、日本の料理文化に触れていただきました。もちろん、日本酒と並んで美味なポルトガル・ワインを召し上がっていただきました。
<草の根交流・姉妹都市交流・青少年交流の促進>
現在、日本とポルトガルの間には7つの姉妹都市関係があります。これまでの私の働きかけにより、ポルトガルの8市長(州首相)から日本との新規姉妹都市提携の希望が寄せられています。日本においても姉妹都市提携に強い関心を示している自治体が出てきており、既に姉妹都市提携に向けて具体的に準備を行っている自治体もあります。私は、人と人との交流である「草の根レベル」での交流は、政府間交流にも増して実に大切だと思っています。その意味で、私は姉妹都市提携を全面的に支援してきました。
その中でも特に力を注いできたのが、「青少年交流」です。私は、現在の世界で最も必要とされる価値観は「寛容」の精神ではないかと考えています。今日、イスラム原理主義、偏狭なナショナリズムなどにより、世界でテロや暴力が台頭しています。より安全で平和な世界・社会を築き上げていくためには、世界の青少年達の水平線、地平線を押し広げ、より大きな寛容の精神を培ってもらうことが重要です。そのために最も大切なことは、若い時から世界の異文化と接触し、異なった物の考え方、生き方を知ってもらうことです。その様な考え方に基づいて、私は、姉妹都市間における青少年交流を促進させるために努力してきました。この私の考えに賛同していただいた日本企業より、青少年交流に対して資金的支援を行っていただけるとの大変寛大なお約束を戴いています。この資金援助は明2009年から動き出します。日本とポルトガル間の非常に良好な友好関係を未来に向けて更に発展させていくためにも、両国の青少年交流が益々活発化していくことを心から望んでいます。
<2010年:日ポ修好150周年記念行事>
2010年は日本ポルトガル修好150周年です。カヴァコ・シルヴァ大統領も、この記念すべき年に両国政府と国民がいろんな事業を実施して行こうではないか、と私に述べられました。在ポルトガル日本大使館としては、この機会に様々な記念事業を実施しようと、既に準備に取り掛かっています。また、ネットワーキングのためのJapanNETを最大限に活用しながら、両国の政府と民間のいろんな団体や個人が一緒になって、この記念すべき年にそれぞれのイニシアティブを発揮して種々のイベントを繰り広げ、未来に向けて更にいっそう友好関係を増進して行こうではありませんか。皆様のご協力とご支援をお願いいたします。
最後になりましたが、在任中に私を支えてくれた皆様に心からの感謝の意を表して、私の離任の挨拶と致します。
»ページTOPへ
新年明けましておめでとうございます。日本大使館のホームページへ、ようこそ!
私は、昨2005年11月ポルトガルに着任いたしました。今回は2回目のポルトガル訪問になります。私が最初にこの地を訪問したのは今から約33年前、サラザール政権時代の最後でした。家内と二人でオンボロ自動車を運転しての旅行でしたが、たくさんの楽しい思い出があります。
あるガソリンスタンドに止まったとき、周りにいた土地の人たちが数名、私たちのうわさをしている様子でした。耳を澄ますと、どうも私たちが夫婦か、それとも未婚の者同士の旅行かをうわさしている様子です。そこで家内が、自分がつけている結婚指輪を指し示しました。そうすると、皆が「あー、そう。」と大変安心した感じで、心から納得してくれた様子でした。私たちは、ポルトガルの人々が「家族」という価値観を非常に大切にしていることを肌で感じました。
また、とある漁村では、ちょうど漁から船が戻ってきたところで、浜辺では競りが始まっていました。私たちは、取れたての海老を分けてもらって、近くの丘の上で海を眺めながら、塩茹でにして食べました。その美味しさは忘れられません。
その後33年の年月を経て、再びこうして思い出の地、ポルトガルに戻ってくることができ、大変嬉しく思っています。
1543年以来の日本とポルトガルの交流の深さは、「パン」「ボタン」「タバコ」「(雨)合羽」「かるた」「襦袢」「伴天連」「金平糖」「ばってら」など、ポルトガル語を語源とする多数の日本語に現れています。
そのような歴史を基礎に、日本とポルトガルはユーラシア大陸の両端にあって、今日、新たな交流を進めてきています。2004年には日本の皇太子殿下がポルトガルを訪問しました。また2005年には、愛・地球博参加のためのサンパイオ大統領の訪日などが行われた他、日・EU市民交流年として、日本とポルトガルの双方において青少年のホームステイ、歌舞伎ワークショップ、能公演といった様々な交流事業が行われました。
私は、これからの数年間、従来にも増して日本とポルトガルの交流を進めて行くことができればと願っています。観光分野での交流、サッカーを始めとするスポーツ分野での交流、青少年の交流、経済分野での交流、文化交流など、多くの分野で交流を深めるためのアイディアや知恵がありうると思います。日本に関心をお持ちのポルトガルの皆様や、在留邦人の皆様などから、そのようなアイディアや知恵をお伺いしながら、また皆様方のご協力を得ながら、両国間の交流の増進に努めて参りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
在ポルトガル共和国大使
原 聰
»ページTOPへ
»「今日の東アジア」
(2006年10月24日、ポルト、葡日商工会議所設立35周年記念セミナー)
»「今日の東アジア」
(2006年10月26日、リスボン、ポルトガル・カトリック大学)
»「東アジアの安全保障」
(2007年 3月 7日、リスボン、防衛研究所)
»「今日の東アジア」
(2007年 5月 8日、リスボン、葡日商工会議所主催セミナー)
»「日本と欧州-世界運営におけるパートナー」
(2007年 6月30日、リスボン、カトリック大学)
(2008年 4月10日、リスボン、「発見の会合」)
»「異文化との共生と民間交流」
(2008年 2月20日、鹿児島県西之表市)
»「日本とポルトガル-異文化との出会い」
(2008年 2月21日、熊本県人吉市第一中学校)
»「異文化との共生と民間交流」
(2008年2月22日、熊本県長洲町)
(2008年 2月22日、熊本高校)
»「日本の精神を垣間見る」
(2008年5月15日、サンタレン)
»「日本人の価値観」
(2008年 9月15日、リスボン、オリエント博物館)
大使インタビュー
»「Villas e Golfe誌」 (2008年 10月号/11月号
(2008年 9月15日、リスボン、オリエント博物館)