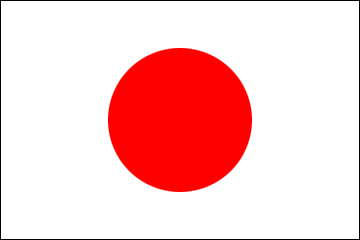渡航にあたっての留意事項
令和3年7月5日
犯罪発生状況,防犯対策
1 犯罪発生状況
ポルトガル政府が発表した2020年の犯罪認知件数は29万8,797件で、前年と比較すると11%減少しました。このうち、殺人、強盗、放火といった凶悪犯罪の認知件数も1万2,469件と、前年より13.4%減少しており、いずれも2003年以降、最も少ない件数となっています。認知件数が多い犯罪は、配偶者等による家庭内暴力(平均64件/日),車上狙い(平均57件/日),電子機器使用詐欺(平均54件/日),暴行(平均50件/日)の順となっています。外国人観光客が狙われる傾向にある置き引き(平均20件/日)やスリ(平均10件/日)、ひったくりを含む路上強盗(平均6件/日)の認知件数も減少しました。ポルトガルはヨーロッパ諸国の中では比較的安全と言われていますが,窃盗被害に遭わないよう十分な注意が必要です。
2 日本人の被害例
大使館に届けられる被害の大半は,スリ・置引きなどの盗難被害です。ポルトガルでは,デビットカード(ムルティバンコ(Multibanco)),またはクレジットカードによる支払いが一般的であるため,地元の人は多額の現金を持ち歩きませんが,外国人観光客は多額の現金を持ち歩いていると思われていることが多く,犯罪者のターゲットとなっています。
日本人の犯罪被害は,リスボンに集中しています。路面電車(28番及び15番)や地下鉄等の公共交通機関の車内や駅・停留所,ベレンの塔やサン・ジョルジェ城等の観光地,バイシャ地区,アルファマ地区,バイロ・アルト地区,空港やホテルのロビー等外国人観光客が多く集まる場所で,スリや置き引きが多発しています。
3 主な犯罪の手口及び対策
(1)スリ
ア 手口
○ 地下鉄やバスで数人組のグループに取り囲まれ,バッグから財布を抜き取られる。
○ 路面電車(特に28番と15番)に乗車する際,割り込んできた犯人に前後を挟まれ,前の人物が切符の検札機で時間を稼いでいる間に,後ろの人物にリュックサックから財布を抜き取られる。
○ 混雑している停留所で路面電車の到着を待っている際,気づかない間にバッグから貴重品を盗まれる。
○ 観光客を装った二人組が地図を広げて道を尋ねてきた際,対応している間にポケットから財布を盗まれる。
イ 対策
○ 外出時は,旅券,多額の現金・カード類,航空券等の貴重品は極力持ち歩かない。
○ やむを得ず持ち歩く場合には,貴重品などは一箇所にまとめず,分散させる。
○ ズボンの後ろポケットやバッグの外側のポケット等,人目につくところに財布や貴重品を入れない。常にバッグの口を閉めておく。
○ 電車やバス等の車内,観光スポット等の混雑している場所では,バッグ等の荷物は身体の正面に抱えるように持ち,歩行中でもリュックサックは背中に背負わない。
(2)置き引き
ア 手口
○ レストランで食事中,椅子にかけていたバッグを盗まれる。
○ ロシオ広場で日本人グループで話をしていたところ,足下に置いていたバッグがなくなっている。
○ 空港,ホテル等で話しかけられるなどして注意をそらした隙に,足下や椅子においていたバッグを盗まれる。
イ 対策
○ 空港,ホテル,レストラン等では,荷物を床や座席に放置しない。
○ 荷物は身体から離さないようにし,足下や座席に置く場合も,常に荷物を確認するなど注意を払う。
○ レストランやカフェ等では,バッグは膝の上等目の届く場所に置き,ビュッフェでは,椅子や机の上に荷物を置いたまま席を離れない。
○ 空港,ホテル,ターミナル駅で見知らぬ者が突然話しかけてきたり,小銭や持ち物を目の前でばらまいたりして,相手の気を引いた隙に,足下や椅子に置いておいたバッグを盗まれることもあるので,常に荷物等に注意を払う。
(3)強盗・ひったくり
ア 手口
○ 両替所や銀行のATMで,親切を装った犯人にナイフやけん銃を突きつけられ金品を奪われる。
○ 夜道を一人で歩いていたところ,暗がりから現れた男に首を絞められ現金等を強奪される。
○ 人気のない通りを歩行中,後方から来たバイクに乗った男に,肩から掛けていたバッグを奪われる。
イ 対策
○ 人気のない通りや夜道での一人歩きを避け,可能な限りタクシーを利用する(当地のタクシーは日本と比較すると料金が比較的安く,気軽に利用できる交通機関です。)。
○ 道を歩く時は,ショルダーバッグ等は車道と反対側に抱えて携帯する。ショルダーバッグをたすき掛けにしていても,カッターナイフ等で皮紐を切られて,強引に盗まれることもあるので注意する。
○ 外を歩く時は,一見して高価とわかる腕時計,ネックレス等の貴金属類は身に付けない。引きちぎるといった乱暴な手口で奪取されることもあり,思わぬ大怪我を負うことがあるので,高価な時計,宝石等は目的地に着いてから身につけるといった配慮が必要。
(4)車上狙い
ア 手口
○ レンタカーを駐車場に止めて観光中,後部座席に置いていたバッグを盗まれる。
○ 観光バスを利用して観光中,目的地に到着後,荷物を座席に置いたままバスを降りたところ,戻ってきたら荷物がなくなっている。
イ 対策
○ 防犯アラーム及び盗難防止装置が付いている車両を使用する。
○ 車両は人通りの少ない場所や人目に付きにくい場所には駐車せず,駐車場がなければ,出来るだけ建物の出入口近くに駐車する。
○ 短時間の駐車でも必ずドアロックをし,車内に貴重品や荷物を放置しない。
(5)暴行
ア 手口
○ サッカーの試合後に,ファン同士のケンカに巻き込まれる。
○ レストランで食事中,酒に酔った男にいきなり殴られる。
イ 対策
○ サッカー観戦の際は,騒ぎを起こしそうなサポーターの近くでの観戦は避け,試合終了後は速やかに退場し,競技場内外で騒いでいるグループには近づかない。
○ 酔っ払いには近づかない。
(6)テロ
これまでに,ポルトガルにおいてテロによる日本人の被害は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア,バングラデシュにおいて日本人が殺害されるテロ事件が発生しています。また,テロは,日本人が数多く渡航する欧米やアジアをはじめとする世界中で発生しており,特に,近年では単独犯によるテロや,一般市民が多く集まる公共交通機関等(ソフトターゲット)を標的としたテロが頻発していることから,こうしたテロの発生を予測したり未然に防ぐことが益々困難となっています。
このようにテロはどこでも起こり得ること及び日本人が標的となり得ることを十分に認識し,テロの被害に遭わないよう,海外安全ホームページや報道等により最新の治安情報の入手に努め,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。
査証,出入国審査等
1 査証・滞在許可について
(1)旅券の残存有効期間について
ポルトガルへの入国に際して必要な旅券の残存有効期間は,「滞在期間+3か月」です。
(2)短期滞在(査証免除について)
日本とポルトガルの査証免除取極に基づき,観光等を目的とする3か月以内の短期滞在の場合には,査証を取得する必要はありません。
なお,ポルトガルが加盟しているシェンゲン協定に関して,2013年10月18日から,同域内において査証を必要としない短期滞在については,「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されます(従来は,「最初の入域日から6か月のうち最大3か月の間」であった規定が変更となったもの)。これにより,無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり,過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されることになります。
また,2013年7月19日から,短期滞在査証免除の対象者についても,有効期間が出国予定日から3か月以上残っており,かつ,10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を保持していることが必要となります。
シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001,URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan ),ポルトガルの措置に関する情報は駐日ポルトガル大使館に問い合わせて必ず確認することをお勧めします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
(3)長期滞在について
3か月を超えて滞在をする場合には,予め査証を取得しておく必要があります。滞在する期間や目的によって取得すべき査証の種類は異なりますが,大別すると次の2種類の査証のどちらかを取得することになります(詳細は,在日ポルトガル大使館にお問い合わせください。)。
ア 一時滞在査証(Visto de Estada Temporária):1年未満の滞在の場合
イ 滞在査証(Visto de Residência):1年以上の滞在が見込まれる場合
なお,査証を取得しないまま,3か月をこえて滞在すると,罰金刑に処せられた上,5年を下回らない範囲で入国が制限されることがありますので,御注意ください。
2 出入国審査
(1)シェンゲン協定加盟国内から入国する場合には入国審査は行われませんが,到着後3営業日以内に最寄りの外国人管理局で入国の届出をしなければなりません。ただし,入国後ポルトガル政府公認のホテル等宿泊施設に宿泊し,宿泊名簿等に記入した場合には,届け出たものとして扱われます。
なお,18歳未満で,ポルトガル国籍又は長期滞在する外国籍の未成年については,同伴の親権者がいない場合,またはポルトガル国内に身元保証人がいない場合には,入国を拒否される場合があるので御注意ください。
(2)上記のとおり,シェンゲン協定域外から域内に入る場合,最初に入域する国において入国審査が行われ,その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
しかし最近,ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が,経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証,(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注),又は(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ,これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
このため,現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には,注意が必要です。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが,シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には,滞在国及び経由国の入国審査,滞在許可制度の詳細につき,各国の政府観光局,我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし,事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により,(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在,(2)シェンゲン協定域内国のトランジット又はドイツへの入国許可を取得。
○シェンゲン協定域内国:26か国
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン
(3)シェンゲン協定加盟国間の国境(陸路)における出入国管理及び税関は原則廃止され,自由に移動ができます。また,空港における審査も一般的には簡素化されています。
但し,治安対策等のため,特にルクセンブルクから列車を利用して隣国との国境を越える場合,車内で警察による旅券(パスポート)検査や所持品検査が行われることがあります。
(4)シェンゲン領域内の移動に際しては,入国審査の有無にかかわらず,日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において,旅券を紛失(盗難を含む)した場合には,速やかに旅券を紛失した場所(国)において,現地警察などへの届出及び最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをしてください。
3 税関
税関検査は以前に比べ厳しくなっていますので,身の回り品を除き必要以上に多量の物品を持ち込まないようにし,段ボール箱による持ち込みは避けた方が賢明です。
なお,欧州連合(EU)域外からの入国時における持ち込み制限は以下のとおりです。
(1)外貨を含めた通貨及び現金化可能な資産
ア 持ち込み,持ち出しは無制限
イ 但し,1万ユーロ相当以上の現金や現金化可能な資産を欧州連合(EU)域内に持ち込む,若しくは域外に持ち出す場合には税関での申告が必要。
(2)土産品
ア 陸路(車両・鉄道),若しくは自家用船舶あるいは航空機で入国する場合:300ユーロ相当まで
イ 自家用でない空路(航空機),あるいは航路(船舶)で入国する場合:430ユーロ相当まで
ウ 15歳未満が入国する場合:150ユーロ相当まで
(3)たばこ類
たばこ200本又は,細葉巻タバコ(1本3グラムまで)100本又は,葉巻50本又は刻みタバコ250グラム
(4)アルコール類
ア 23度以上の酒又は80度以上の非変性エチルアルコール 1リットル 又は 22度以下の酒 2リットル
イ ビール 16リットル
ウ 非発泡性ワイン(スパークリングワイン,ヴィーニョヴェルデ,ポルトワイン,モスカテル・マデイラワイン等を除く) 4リットル
(5)燃料類
車両等の燃料タンクに入っている燃料,又は携帯容器入りの燃料10リットル
※タバコ類,アルコール類,燃料については,17歳未満が持ち込む場合には免税対象とはならない。
※麻薬類,銃砲類は輸入禁制品です。
その他詳細につきましては,以下のポルトガル税関のホームページを御確認ください。http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_aduaneira/viajantes/bagagem_pterceiro_2009/Pages/iva-iec-isencao-2009.aspx
滞在時の留意事項
1 身分証所持義務
ポルトガルでは常時身分を証明するもの(パスポート)を所持する必要があります。
2 写真撮影の制限
軍関係施設及び空港施設については,写真撮影が制限されています。
3 薬物の取締り
コカイン,クラック,マリファナ,ヘロイン,LSD,覚せい剤等の主要禁止薬物を輸入し,譲り渡しまたは譲り受け,所持した者は,通常は最長12年の禁固処分となります。
4 賭博行為
公営のカジノ,福祉団体が主催する宝くじ等があり,外国人も購入できますが,不法賭博を犯した場合は処罰されます。当局が管理する合法的なカジノ以外での賭博行為は,2年以下の禁固及び罰金に処せられます。
5 車の運転について
(1)運転免許証について
ポルトガルでは、日本の公安委員会発行による有効な運転免許証をお持ちであり、かつ以下の条件を満たす場合、ポルトガル国内に限り同免許証での運転が可能となっております。
・60歳未満であること
・運転免許証の発行または更新日から15年以上経過していないこと
・ポルトガルまたは日本において、交通違反による免許停止や取消し処分等を受けていないこと
(2)一般的な交通ルール
右側通行で,信号のない交差点では右側車両優先となります。ただし,ロータリー(ロトゥンダ)では,ロータリー内にいる車が進入しようとする車より優先権を持ちます。
法定制限速度は,市街地50km/h以下,郊外一般道路70~90km/h,高速道路120km/hとなっており,日本の道路に比べ制限速度が高くなってます。
シートベルトは,助手席,後部座席も含めて全員に着用が義務付けられており,違反者は処罰(罰金)されます。
(3)道路事情・運転マナー
ア 道路事情
市街地では,石畳の道,狭く曲がりくねった道,路上駐車が多いため,非常に運転が難しくなっています。また,リスボン市やポルト市では路面電車の軌道敷上を走ることもあり,雨の日はスリップするなど,より運転しにくくなっています。
高速道路は,最近になって整備された道路も多く,走行しやすくなっているものの,当地の運転マナーは必ずしも良くないため,周囲の車には注意が必要です。
イ 運転マナー
日本と比べると,総じて運転者,歩行者のマナーは良くありません。車の運転は一般に乱暴で,車間距離もあまりとらず,また,道幅が狭く相互通行困難な場合でも徐行せず運転することが多く見られます。走行速度,一般道,高速道路問わず,制限速度を大幅に超過する車が多く,方向指示器なしでの車線変更も頻繁に行われます。また,歩行者も信号を守ることは少なく,横断歩道の無い場所でも平気で横断しています。
運転を行う際には,周囲の車の動き,歩行者の動きに注意し,高速道路など速度が超過しやすい道路では,後方から接近する車の動きにもご注意ください。
<レンタカーの利用>
レンタカーは,空港,主要駅周辺では利用に不自由はしません。しかし,地方では借りられる場所が限定される場合がありますのでご注意ください。
(4)交通違反の罰則について
交通違反の罰則は強化されており,それに伴い,飲酒運転の検問等の取締りも強化されています。
外国人旅行者等の短期滞在者が違反した場合には,その場で最高限度額の支払いを求められるか,帰国後,レンタカー会社を通じて,反則金の支払いを求められる場合もありますので御注意ください。
6 在留届
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ポルトガル日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(オンライン在留届,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在ポルトガル日本国大使館まで送付してください。
7 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は,滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は,ポルトガルで事件や事故,自然災害等が発生した際に,在ポルトガル日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。
8 子供を連れて旅行する場合の注意
ポルトガルでは,仮に片親だけで子供を連れて旅行をする場合に,もう一方の親権者による委任状等を所持していないと,各国の子供を誘拐する行為として,重大な犯罪とされる場合があります。
ポルトガルでは,刑法の規定により,「未成年者を連れ去る」などの行為が, 2年以下の禁固刑又は,240日以下に相当する罰金が科せられますので,御注意ください。
9 ハーグ条約
ポルトガルは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページを御覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
風俗,習慣,健康等
1 習慣
スペインのようなシエスタ(昼休み)の習慣はなく,商店等が休業することはありませんが,昼食は1時頃から十分に時間をかけて取る習慣がありますので,飲食店では待つこともあります。また,夕食の時間も日本に比べ遅く,レストランなどの飲食店は,夜7時半以降でないと開店しないお店が多いので御注意ください。
国民の大多数がカトリックのため,都市部でも観光地,サービス業を除けば日曜日は安息日となり,個人商店はほとんど閉店します。
教会の多くは出入り自由ですが,熱心な信者の祈りを妨げるような行為は厳に慎まなければなりません。観光客が多く集まる有名な寺院,修道院付設の教会等でも同様の注意が必要です。また,女性は肌の露出が多い服装は敬遠される事が多いので注意しましょう。
2 気候,食習慣等
当地の気候は,年間を通じておおむね温暖で過ごしやすいですが,夏など朝晩の寒暖の差が大きいため,服装には注意を払う必要があります。
夏夏期(5月~9月)は,ほとんど雨が降ることがなく,非常に乾燥しており日差しも強いため,熱射病を避けるためにも帽子を着用し,こまめに水分補給を行うことをお勧めします。
それ以外の時期(10月~4月)は,雨が多くなります。また,朝天気が良くても午後には雨が降るなど,天候が変わりやすい時期となりますので,折り畳み傘など雨具の準備が常に必要となります。
飲食物の汚染等に基づく中毒等の心配はありませんが,水道水には石灰分が多く含まれていること等から,ミネラル・ウォーター(アグア・ミネラル)の飲用をお勧めします。
3 医療事情
(1)医療機関は,公立病院,公立診療所,私立病院,個人医の4種類がありますが,医療水準はヨーロッパの中では低い部類です。
当国の社会保険に入っている場合,公立病院では,診察料金が低額若しくは無料で受診ができますが,そのため非常に混雑しており,入院病棟も病床が常に不足しています。
私立病院は,設備面ではほぼ問題がありませんが,社会保険は適用されず一般的に診察だけで100ユーロ程度,入院するだけで1日約200ユーロ程度の高額の費用が必要となります。
軽い風邪薬,腹痛薬,頭痛薬,消毒薬,及び軟膏など,簡易な治療薬は処方箋が無くても薬剤師に相談の上購入することができます。しかしながら,日本人の体質に合わないものもありますので,常備薬は日本から持参されることをお勧めします。
(2)当地は,特異な風土病もないので,入国にあたって義務づけられた予防接種もありません。また,蚊も少ないため蚊を媒介とする伝染病の発生例もあまり見受けられません。ただし,大西洋上のマデイラ諸島は海洋亜熱帯性の気候で,蚊も多いため,デング熱等蚊を媒体とする伝染病に気をつける必要があります。マデイラ諸島へ行かれる際は,虫除けを準備するなど虫さされに対する注意が必要です。なお,以下の厚生省検疫所ホームページも併せて参考にしてください。
●感染症情報(http://www.forth.go.jp)
緊急時の連絡先
◎非常用(警察・救急) :112◎在ポルトガル日本国大使館:(+351)21-3110560
※在留邦人向け安全の手引き
その他の詳しい情報は,現地の在外公館(日本大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」を御参照ください。
問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)5367
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○在ポルトガル日本国大使館
住所:Av. da Liberdade, No 245-6o, 1269-033 Lisboa, PORTUGAL
電話:21-311-0560
国外からは(国番号351)-21-311-0560
ファックス:21-353-7600
国外からは(国番号351)-21-353-7600
ホームページ:https://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html