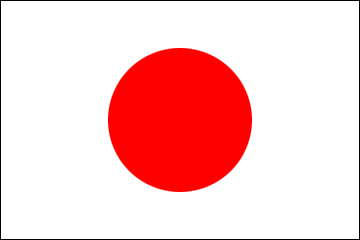雅楽ワークショップ(報告)
平成28年2月4日


1月21日、リスボン高等音楽院において、雅楽の笙(しょう)演奏家兼現代音楽作曲家・真鍋尚之と、箏(こと)奏者・梶ヶ野亜生による、笙及び箏のワークショップ並びにミニコンサートが行なわれました。ポルトガルでは、日本の皇室に宮廷音楽として継承される雅楽で用いられるこれら楽器の事業は珍しく、実際に楽器を目にできる貴重な機会となりました。
笙演奏家の真鍋氏より、雅楽はアジア諸地域の影響を強く受け千年以上に亘り日本の皇室で演奏されてきたこと、楽譜ではなく口承により代々伝えられてきたことなど説明があり、雅楽特有の旋律を実演し雅楽の発展についてビデオによる紹介を行ないました。また、雅楽を奏でる楽器の一つとしての笙の起源・構造及びその発展について解説を行ない様々な音を実演しました。
箏奏者の梶ヶ野氏より、初期の箏は5弦であり後の奈良時代に弦数が13弦に増え長さが2メートル近くになったこと、箏はもともと中国からもたらされた楽器で後に日本の皇室で演奏されるようになったこと、箏は木製で弦は本来は絹で作られていたこと(現在はテトロン製が主流)、右手の3本の指に爪をつけて演奏を行ない、左手で音程を変えたり弦を押さえることなどを説明しました。各楽器による伝統音楽の演奏や両者による現代音楽の演奏を通じ、楽器の持てるポテンシャルを実証しました。
ワークショップに参加した同校の学生達は、独特の音色を持つ珍しい日本の伝統楽器に大いに興味を示し、イベントは活発な質疑応答で締めくくられました。
実施会場として本イベントを受け入れていただいたリスボン高等音楽院並びに参加いただいた同校の学生の皆様に感謝申し上げます。